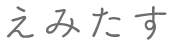「うちの子、発達障害かも?」と思ったら──不安な気持ちと今できること
気づいた瞬間の、あの複雑な感情
他の子と比べて、なんだか違う気がする。
集団行動が苦手、こだわりが強い、言葉が遅い──。
「もしかして、発達障害?」
その瞬間、頭の中がぐちゃぐちゃになりませんでしたか?
保護者が抱える3つの葛藤
1. 認めたくない気持ち
「気のせいかもしれない」「そのうち追いつく」
そう思いたい気持ち、すごくわかります。
誰だって、我が子に困難があってほしくないから。
2. 早く動くべきか迷う不安
「診断を受けたら、レッテルを貼られるんじゃないか」
「でも、何もしないで手遅れになったら…」
動くべきか、様子を見るべきか。正解がわからない。
3. 自分を責めてしまう罪悪感
「私の育て方が悪かったのかな」
「もっと早く気づいてあげるべきだった」
でも、それは違います。誰のせいでもないんです。
大切なのは「診断」より「今できること」
診断を急ぐ必要はありません。
焦らなくて大丈夫です。
まずは、お子さんを「理解する」ことから始めましょう。
今日からできる3つのステップ
ステップ1:お子さんの「得意」と「苦手」を観察する
- 何をしている時、機嫌がいい?
- どんな場面でパニックになる?
- どんな伝え方だと理解してくれる?
メモに残すだけでOKです。
パターンが見えてくると、対応が変わります。
ステップ2:環境を「ちょっとだけ」調整してみる
発達障害かどうかに関わらず、環境調整は効果的です。
【具体例】
- 視覚支援:やることを絵カードで見せる
- 感覚調整:うるさい場所を避ける、触覚が敏感なら服のタグを切る
- 予告:「あと5分で終わるよ」と事前に伝える
- 選択肢を減らす:「何食べる?」より「AとBどっち?」
小さな工夫で、子どもの困り感が減ります。
ステップ3:一人で抱え込まず、相談する
「まだ診断受けてないから…」と遠慮しないでください。
【相談できる場所】
- 保育園・幼稚園・学校の先生
- 自治体の子育て相談窓口
- 発達支援センター(診断なしでも相談可)
- 保健センターの心理士
「診断前でも相談していい」んです。
専門家は、診断の有無に関わらず、お子さんに合った関わり方を一緒に考えてくれます。
診断を受けるかどうかは、焦らずに
診断を受けるメリットもあります。
- 支援制度が使える
- 園や学校で配慮してもらいやすくなる
- 親自身が「どう関わればいいか」理解できる
でも、診断がゴールではありません。
大事なのは、お子さんが安心して過ごせること。
診断は「必要だと感じた時」で大丈夫です。
あなたは、もう十分頑張っています
「うちの子、発達障害かも」と気づいた時点で、あなたは素晴らしい親です。
気づいて、調べて、悩んで、ここまで来たんですから。
完璧な親なんていません。
お子さんに必要なのは、「理解しようとしてくれる人」。
それは、もうあなたです。
まとめ:今日からできること
✅ お子さんの得意・苦手を観察する
✅ 小さな環境調整を試してみる
✅ 一人で抱え込まず、誰かに相談する
一つずつ、焦らず、お子さんのペースで。
あなたとお子さんが、少しでもラクに、笑顔で過ごせますように。